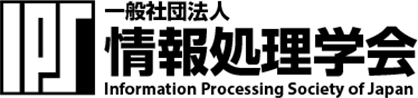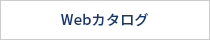「近年の生成AIブームに思うこと」
吉濱 佐知子(技術応用担当理事)
2023年に技術応用理事を拝命し、早くも2年近くが経過しました。それ以前の総務理事時代と合わせると、4年間情報処理学会の理事を務めさせていただいたことになります。この間、私自身も研究職から技術コンサルタントに転職するなど変化がありました。一方で、社会では生成AIの登場以降、その活用が目覚ましいスピードで進み、日々の仕事や生活様式に変革をもたらしつつあります。
私のコンサルタントとしての業務でも、特に昨年から生成AI活用に関する支援ケースが劇的に増えています。当初は小規模な技術検証や概念実証が中心でしたが、その後、実用的なビジネスアプリケーションへの展開を目指す企業が増え、「AIチャットボットを超えて、どのようにビジネス価値を創出するか」が検討課題となっています。さらに最近では、全社的なAIプラットフォームの構築や、AIエージェントの活用に対する注目と期待が高まっており、この動向は当分続きそうです。
私自身も業務で生成AIツールを活用し効率化を図ることが増えました。たとえば、以前は資料の翻訳を手作業で行っていましたが、最近は生成AIに翻訳させた方が速く、しかも(悔しいことに)文法エラーも少なそうだと気づいてしまいました。そこで、生成AIに一次翻訳させた上で内容をチェックする、あるいは自分の翻訳を生成AIに推敲させるといったハイブリッド方式を採用しています。プログラミングの際も、自然言語で要件を示すとコードを生成してくれるツールが普及し、まずはコード生成から始めて動作や詳細を確認する流れに変わってきました。最近はAIエージェント技術により、色々なトピックに関して調査して資料を作る、みたいなことまで自動でできるようになり、仕事は楽になる一方で、「数年後にはコンサルタントの仕事がなくなるのでは」と危惧する面もあります。実は、この「理事からのメッセージ」を書く際も、多忙だったので生成AIに書かせてしまいたい欲望がムラムラと湧き上がりましたが、そこはグッと我慢して自分で書くことにして、なんとか人間の尊厳を維持しています。
業務の中で生成AIを活用して生産性を向上することは、今後の社会生活の中では避けられないと思います。むしろ、企業としての競争力を維持していくためには不可避であると思います。一方で不安になるのは、生成AIに頼り切ってしまい、自分で考えたり、創造したりすることを放棄してしまう方が、一定数いるように見えることです。大人でもそうですから、子供にとっては一層その傾向が強くなると思われます。AIが人間より賢くなり、そしてAI自身がAIを賢くするような技術が登場している中、それでもあまり困らないのかもしれません。しかし、皆が考えることを放棄し、AIに頼り切る世界はバラ色の未来ではなく、ディストピアではないでしょうか。
さて、私が担当する連続セミナーでは、2025年度は「AIが拓く次世代イノベーション」と題し、昨年に引き続きAIをメインテーマとして取り上げます。学会ならではの中立的な技術情報を提供していく予定です。過去数年はオンライン開催でしたが、今年はオンラインに加えて久しぶりにハイブリッド開催も試行することとなり、人と人との対面のコミュニケーションで生まれるセレンディピティへの期待が高まります。
すべてをAIに委ねるのではなく、AIをツールやコンパニオンとして上手に活用し、人間ならではの創造的作業に時間を使えるようにすることで、考える喜びや創造の楽しみを追求しませんか? 連続セミナーをはじめとする情報処理学会の活動が、そのような意識を持ち行動するきっかけとなれば幸いです。