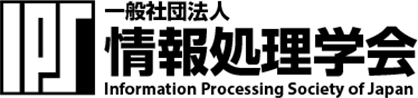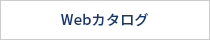役員名簿(2024年度)
2024年度役員名簿
※リンクは改選時の略歴・抱負、氏名*は女性
過去の役員名簿はこちら
| 役職名 | 担当職務 | 氏名 | 所属 | 就任年月日 | 学会勤務 |
| 会 長 | 法人 代表 | 森本 典繁 | 日本アイ・ビー・エム(株) 副社長執行役員 最高技術責任者兼研究開発担当 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 副会長 | 会長補佐 | 田島 玲 | LINEヤフー(株)LINEヤフー研究所 所長 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 副会長 | 会長補佐 | 砂原 秀樹 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 論文誌 | 井上 美智子 | 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 総務 | 小野 智弘 | (株)KDDI総合研究所Human-Centered AI研究所 所長 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 標準化 | 河合 和哉 | (国研)産業技術総合研究所インテリジェントプラットフォーム研究センター超分散トラスト研究グループ 招聘研究員 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 調査研究 | 斉藤 典明 | 東京通信大学情報マネジメント学部 教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 会誌/出版 | 櫻井 祐子 | 名古屋工業大学 教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 企画 | 首藤 一幸 | 京都大学学術情報メディアセンター 教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 財務/情報システム・DX | 田村 孝之 | 三菱電機(株)情報技術総合研究所データマネジメントシステム技術部 部長 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 事業 | 中山 泰一 | 電気通信大学大学院情報理工学研究科 教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | IT産業連携 | 長谷川 亘 | 京都情報大学院大学/京都コンピュータ学院/京都自動車専門学校 総長・理事長・教授, (一社)日本IT団体連盟 代表理事・筆頭副会長 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 教育 | 湊 真一 | 京都大学大学院情報学研究科 教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 技術応用 | 吉濱 佐知子 | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 Professional Services bigdata consultant | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 理 事 | 論文誌 | 稲見 昌彦 | 東京大学 総長特任補佐・先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 長期戦略 | 大場 みち子 | 京都橘大学工学部情報工学科 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 調査研究 | 緒方 広明 | 京都大学学術情報メディアセンター 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 総務 | 鎌田 真由美 | 日本マイクロソフト(株)サービス事業本部 ソリューションアーキテクチャー本部 本部長 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 調査研究 | 岸 知二 | 早稲田大学理工学術院創造理工学部 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 事業 | 木村 朝子 | 立命館大学情報理工学部 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 会誌/出版 | 高岡 詠子 | 上智大学理工学部 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 財務/情報システム・DX | 千葉 直子 | NTT社会情報研究所 主席研究員 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 企画 | 塚本 昌彦 | 神戸大学大学院工学研究科 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 長期戦略 | 寺⽥ 努 | 神戸大学大学院工学研究科 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 教育 | 遠山 紗矢香 | 静岡大学情報学部 准教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 理 事 | 技術応用 | 山下 直美 | 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 教授 | 2024年6月5日 | 非常勤 |
| 監 事 | 監査 | 中野 美由紀 | 情報・システム研究機構/津田塾大学 理事/教授 | 2023年6月7日 | 非常勤 |
| 監 事 | 監査 | 長谷川 輝之 | KDDI(株)次世代自動化開発本部オペレーション技術開発部 シニアエキスパート | 2024年6月5日 | 非常勤 |
※以上、国家公務員出身者(本府省課長・企画官相当職以上および地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上の経験者)の該当はありません。 また、役員報酬の支給はありません。
■役員区分

■会 長
森本 典繁(MORIMOTO, Norishige)(慶大1987卒)
日本アイ・ビー・エム(株) 副社長執行役員 最高技術責任者兼研究開発担当
[略歴] 1987年日本IBM大和研究所.1995年米マサチューセッツ工科大学計算科学科コンピューターサイエンス(EE&CS) 修士(MS)修了, 米MITメディアラボ研究員(1993-1995), 米IBMワトソン研究所勤務(2006-2009), 日本IBM東京基礎研究所長(2009-2015), IBMアジア太平洋地域CTO(2015-2016), 日本IBM常務執行役最 高技術責任者(2021)などを経て現職. 専門分野はデジタル信号処理, 人工知能, 量子コンピューター等. 現在経済産業省半導体デジタル戦略会議委員, 国内外複数企業の外部技術アドバイザー, 大学院大学至善館院特任教授, テンプル大学日本校外部理事等を務める. 慶應義塾大学矢上賞(2012)を受賞.
[抱負] Post-COVIDの新時代に向かって歩み出す国がある一方で, 未だ感染拡大に追われている地域もあります. COVID以前から兆しを見せていた大国間の分断はより顕著となり, 世界各地で地政学的なリスクも高まっています. その政治・経済に与える影響から世界的なサプライチェーンや各産業の構造変革まで様々な変化が起きています. 一方, 環境, エネルギー, 食糧, 医療など, 我々人類を取り巻く喫緊な社会課題の多くは未解決なままです. これらは一部の国や地域だけでは解決できないものであり, 我々が国家, 理念や信条を超えて叡智を結集して当たらなければなりません. この様な時代だからこそ科学技術を通じた交流を維持・促進し平和的な国際協業を推進し続ける事が重要であり, 様々な壁を越えた知の交流を担う学会が果たせる役割は今まで以上に高くなっていると思います. 広く社会や若い世代の声に耳を傾け, 時代の要求に応える様な学会活動を行なって行きたいと考えています. 多様性や国際的な連携も強化し, 社会課題の解決に向けて貢献できる様, 本会に関係する全ての方と一緒に成長していけたらと考えております.

■副会長
田島 玲(TAJIMA, Akira)(東大1990卒)
ヤフー株式会社Yahoo! JAPAN研究所 所長
[略歴] 1992年東京大学工学系研究科修士課程修了. 日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所(1992-2002年, 2005-2011年). A. T. カーニー(2002-2005年)を経て2011年ヤフー入社. 2012年より現職. データ利活用にかかわる研究開発および現場での展開に従事. 博士(理学). 本会理事(2018-2019年度).
[抱負] 個人的なことですが, どちらかというと文系の素養を見せていた娘2人が最近揃って情報系の進路を選択し, 時代の変化を感じております. AIの社会実装, 各業界でのDXの進展に続き, 情報教育が立ち上がり, 情報処理の社会的な認知度, 期待, 裾野の広がりはこれまでにないレベルになってきています. はるかに大きくなった母集団から輩出される優秀な若手人材が近い将来合流してくることが楽しみでなりません. 一方で, 情報処理学会がこの流れにどう寄り添い, 貢献していくか, これからの数年間は非常に重要になってきます. 技術的知見, 議論や発信の場としての価値, 産学連携の体制といった本会の強みが広く認知され求心力となっていくべく, 変化の速いweb業界にあって最先端の技術やデータを現場で活かす取り組みを続けてきた経験をもとに, 橋渡しとなる取り組みを推進することで貢献できればと考えております.

■副会長
砂原 秀樹(SUNAHARA, Hideki)(慶大 1983卒)
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授
[略歴] 1988年慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程単位取得退学. 工学博士. 電気通信大学情報工学科助手, 奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター助教授, 教授を経て, 2008年より現職. インターネット, セキュリティに関する研究に従事. 本会理事(2009年度-2010年度, 2012年度-2013年度),監事(2017年度-2018年度)等を歴任. 本会フェロー. 本会功績賞受賞.
[抱負] 人工知能,メタバース,分散台帳,量子コンピュータなど,これらの技術が社会に浸透し大きく変えようとしています.このような中で正しく情報技術の意味を伝え,社会の中で活用していくことを先導することは情報処理学会の大きな役割だと考えています.そのため,さまざまな観点でのコミュニティの拡大が強く本会に求められるようになってきています.これを実現するためこれまで本会を支えてきていただいた皆様の知見を大切に活用させていただくと共に,これからの世代へそれらを継承しながらカバーする領域を広げ新しい環境への適応を進めていくことが必要です.皆様と共に会員を中心としたオープンなコミュニケーションの場を展開すること,そして実社会を見据えたさまざまな分野との連携を強化することとともに,ジュニア会員を中心とする次世代が活躍する場を提供し展開していくことを迅速に進めなければなりません.これらの目標を見据え,これまで本会が果たしてきたことを尊重しつつ,新しい時代に対応した展開に貢献することができれば幸いだと考えます.

■理事[論文誌担当]
井上美智子*(INOUE, Michiko)(阪大1987卒)
奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授
[略歴] 1989年大阪大学大学院博士前期課程修了,同年(株)富士通研究所入社.1992大阪大学大学院博士後期課程進学, 1995年同修了, 同年奈良先端科学技術大学院大学助手, 2001年同助教授, 2011年より同教授.2003-2005年度本会関西支部幹事.
[抱負] Society5.0, DXなど,情報処理技術は現在そして未来の社会と大きく関わっています. 研究者が交流することで新しいアイディアを思いつく,研究会で発表し意見交換することで研究をさらに発展させる,研究成果を広く世の中に発信して社会応用へとつなげる,子供達が情報処理技術に触れる場を創り未来の担い手をこの分野に導くなど,学会は様々なフェーズで情報処理技術の開拓・発展・普及に貢献しています. 多様な人々が情報処理に関わる多様な分野で活き活きと研究し,情報処理技術のさらなる発展に寄与できるような環境づくりに貢献できればと思います.

■理事[総務担当]
小野 智弘(ONO, Chihiro)(慶大1992卒)
(株)KDDI総合研究所 Human-Centered AI研究所 所長
[略歴] 1994年慶應義塾大学理工学研究科修了後, 国際電信電話(現KDDI)入社. 2022年より現職. この間, 情報推薦, 行動分析, 行動変容, 実世界AI等の研究に従事. 本会シニア会員. JSTさきがけ「文理融合による人と社会の変革基盤技術の共創」領域アドバイザ. 通信文化協会前島密賞(2020). 博士(工学).
[抱負] あらゆる産業・セクションでデジタルトランスフォーメーション(DX)が推進され, 研究者や技術者のみでなく, 文系出身者や長年技術系でない業務に携わっていた社員が, DXに取り組み始めたという声を私の周りでもよく聞くようになりました. 学会の更なる発展には, 研究者の専門性を深めるのみならず, 「情報処理技術やその応用方法を幅広く身につけたい」「特定の分野の研究者と交流・連携したい」「特定の産業領域の専門家やビジネス部門と交流・連携したい」など多様な要望を持つ, 若手からベテランまでのあらゆる世代・立場の方々の成長や活動に役立つ機能やサービスを幅広く強化し, それが必要な方々に届くよう広く発信することで, 会員の皆様の満足度を向上し裾野を拡大することが重要と考えております. 理事に選任されましたならば, 企業で国内外の産学連携を含む研究開発, ならびに, 様々な業態や規模の機関と一緒に研究開発成果のサービス化などに携わったこれまでの経験を活かし, 微力ながらも, 学会の発展へ貢献していきたいと考えております.
■理事[標準化担当]
河合 和哉(KAWAI, Kazuya)(横浜国大1985卒)
国立研究開発法人産業技術総合研究所インテリジェントプラットフォーム研究センター超分散トラスト研究グループ 招聘研究員 ※情報規格調査会からの推薦
[略歴] 1987年横浜国立大学大学院工学研究科電子情報工学専攻修了.同年松下通信工業(株)入社.以来,システム開発,技術渉外に従事し,2005年より国際標準化に従事.情報規格調査会副委員長(2014年より)SC31専門委員会委員長(2011-2016年).SC41専門委員会委員長(2017年より).2020年より現職.
[抱負] 標準化担当理事は, ISO/IEC JTC 1の国内審議団体である情報規格調査会の委員長として, 日本の情報技術の標準化を担うことになります.Society 5.0の実現に向けて,情報技術の果たすべき役割は, そのますますその重要性を増しており,それに伴って情報規格調査会の果たすべき役割, 情報規格調査会への期待は大きくなっているものと認識しています.2011年からJTC 1で具体的な規格開発を担うSCに対応する専門委員会の委員長として,国際標準化の前線で活動してきました.また, 2014年から2期,副委員長として伊藤委員長を補佐しながら情報規格調査会の運営に参画してきました.これらの活動を通じて,現在の情報規格調査会の課題は十分に認識しているつもりです.特に情報規格調査会の経営基盤の安定, 標準化人材の育成は大きな課題だと認識しています. 役員に就任いたしましたら, これらの課題の解決に向けて, 情報処理学会本部, 役員の皆様のご意見を伺いながら取組んでまいる所存です.

■理事[調査研究担当]
斉藤 典明(SAITO, Noriaki)(法政大1988卒)
東京通信大学情報マネジメント学部 教授
※調査研究運営委員会からの推薦
[略歴] 1990年法政大学大学院修士課程修了.同年日本電信電話(株)入社.1999年奈良先端大博士後期課程(社会人)修了・博士(工学).2018年より東京通信大学教授(現職).知識共有, ネットワークサービス, 情報セキュリティ, メディア教育に関する研究開発および実用化に従事.本会グループウェアとネットワークサービス研究会運営委員,幹事および主査等を歴任.
[抱負] この2年間,COVID-19の世界的流行により様々な活動がオンライン化しました.また,2020年からのプログラミング教育必修化は,小中学校だけでなく大学教育においても関心が高まっており,理系文系問わず,多くの学生が情報技術を積極的に学ぶようになりました.情報技術の必要性が社会で広く認知されるとともに,情報技 術を用いて様々な社会問題を解決することが期待されています.情報処理学会の活動は,そのような社会問題を解決し社会を豊かにしてゆく研究開発成果を世の中に送り出す役割を担っていると言えます.これまでの企業研究者としての経験,大学教員としての経験,本会研究会主査としての経験などを活かして,会員の皆様の様々な研究成果が世の中へ羽ばたいていけるように,微力ながら貢献したいと思っています.

■理事[会誌/出版担当]
櫻井 祐子*(SAKURAI, Yuko)(奈良女大1995卒)
名古屋工業大学 教授
[略歴] 1997年名古屋大学大学院多元数理科学研究科博士前期課程修了.2006年九州大学大学院システム情報科学府博士後期課程修了.博士(工学).1997年よりNTTコミュニケーション科学基礎研究所.以降,Yahoo!JAPAN研究所,九州大学准教授,産業技術総合研究所などを経て,2022年より名古屋工業大学教授.
[抱負] 情報処理技術は社会の様々な重要な意思決定に用いられるようになりました.一方,その決定に対する説明可能性や透明性が人々から求められるようになってきています.我々,情報処理技術に携わる者は,それらの社会的要請に答えるべく研究開発や人材育成に努める必要があります.情報処理技術は汎用性のあるグローバルなものですが,それが適用される社会的課題は国により異なります.日本は少子高齢化やエネルギー問題などで「課題先進国」とも呼ばれており,日本オリジナルの研究開発は世界において一層の貢献が期待されています.本会は情報処理技術分野で日本最大の学会であり,産業界と学界を繋ぐ場として,その役割の重要性は増すと考えます.私は企業や国立研究開発法人の研究者,大学教員としての経歴を生かして,日本オリジナルの研究やコミュニティの創出に貢献したいと思います.

■理事[企画担当]
首藤 一幸(SHUDO, Kazuyuki)(早大1996卒)
京都大学学術情報メディアセンター 教授
[略歴] 2001年早稲田大学博士後期課程修了.博士(情報科学).産業技術総合研究所研究員,ウタゴエ(株) 取締役CTO,東京工業大学准教授を経て,2022年より現職.分散システム,ネットワークの研究に従事.IPA未踏PM,(株)アーリーワークス顧問,エンジニア対象投資ファンドMiraise メンター,GMOインターネットグループ(株) 技術顧問等を兼任.
[抱負] 本学会の目的は, 学術, 文化, ならびに産業の発展に寄与すること, とあります. 学会には, そうした社会への貢献に加え, もう1つの面, 会員の側への貢献という目的・役割もあります. 例えば研究会は, そこで磨かれた研究成果が社会の価値になるだけでなく, 同時に, 会員自身も情報交換や交流のメリットを享受するという大変うまい仕掛けです. 今や, 情報技術の関係者はとても多様化しています. 従来通り, 研究機関や大企業の技術者・研究者はもちろん, 情報技術が価値創出の源泉となったあらゆる産業, 情報システムとともに暮らすようになった市民, 皆, 情報技術の関係者となりました. 誰しも, 本会の恩恵を享受し得るという意味においては, すでに会員のようなものです. 私自身の, 私大の学生, 国研の研究職, 辞めて, スタートアップの取締役CTO, 国立大学の教員という様々な経験で得た視点を活かし, 幅広い関係者が学会のメリットを享受できるよう, 尽力致します.
■理事[財務担当]
田村 孝之(TAMURA, Takayuki)(東大1991卒)
三菱電機(株)情報技術総合研究所データマネジメントシステム技術部 部長
[略歴] 1996年東大院情報工学博士課程単位取得退学,博士(工学).1998年三菱電機(株)入社,2020年より現職.並列データベース処理,Webアーカイビング等に関する研究開発に従事.本会論文誌データベース編集委員(2013-2016年度),モバイルコンピューティングと新社会システム研究会幹事,DICOMO2023シンポジウム実行副委員長.
[抱負] デジタル化が急速に進展し,データの重要性が社会のさまざまな分野に浸透するとともに,データを知識や価値に昇華する情報処理技術もこれまで以上の活用が見込まれます.デジタル化社会を支える情報処理技術の体系化と普及に対する本会の役割はますます高まっています.一方,データ活用の現場では,細分化・複雑化した技術を知悉した技術者を確保することは困難になり,ドメインの知見を持った人材へのリスキリングを進める必要があります.そのためには本会がコミュニティとして,研究者やドメイン技術者とつながって相互に課題を共有する場を提供することが 重要と考えます.私はこれまで,データベース技術の研究者として本会の研究会や論文誌でお世話になるとともに,企業でのシステム開発の現場に携わってきました.これらの経験を活かし,本会がデジタル化社会で中心的な役割を果たせるよう,微力ながら貢献していきたいと思います.

■理事[事業担当]
中山 泰一(NAKAYAMA, Yasuichi)(東大1988卒)
電気通信大学大学院情報理工学研究科 教授
[略歴] 1993年東京大学大学院修了.博士(工学).同年より電気通信大学において,計算機システム,並列分散処理,情報教育の研究に従事.2020年度-2021年度本会教育担当理事.2014年度学会活動貢献賞,2016年度山下記念研究賞,本会フェロー.2017年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞受賞.日本学術会議特任連携会員.国立情報学研究所客員教授.
[抱負] 私は,2018年から2020年まで論文誌ジャーナル編集委員会編集長として,2020年から2022年まで教育担当理事として,本会の活動に係わってきました.情報処理教育委員会の活動の一環で,全国大会に中高生情報学研究コンテストを創設し,中高生に本会のジュニア会員となり情報学の探究に取り組んでもらうことを目指しました.また,大学入試で情報入試を普及させるための活動に取り組みました.2022年度から実施されている高等学校の新学習指導要領では,プログラミング,データ活用などを扱う「情報I」「情報Ⅱ」が設けられました.文部科学省は2025年からの大学入学共通テストに「情報Ⅰ」の出題を決め,国立大学協会は「情報Ⅰ」を含む6教科8科目の受験の原則を決めています.この数年間は,本会がこれまでわが国の情報学分野をリードしてきたその成果を,広く国民全体に広げていくための重要な期間です.この成否が,本会はもとより,わが国の将来をも左右すると言っても過言ではありません.これからも引き続き,本会の活動を通して,社会に貢献して行きたいと考えております

■理事[IT産業連携担当]
長谷川 亘(HASEGAWA, Wataru)(早大卒,(米国)コロンビア大学ティーチャーズカレッジ(教育大学院)卒)
京都情報大学院大学/京都コンピュータ学院/京都自動車専門学校 総長・理事長・教授, (一社)日本IT団体連盟 代表理事・筆頭副会長
※理事会からの推薦
[略歴] 早稲田大学卒業,(米国)コロンビア大学ティーチャーズカレッジ(教育大学院)文学修士号(M.A.)取得,(米国)コロンビア大学ティーチャーズカレッジ(教育大学院)教育学修士号(M.Ed.)取得,米国ニューヨーク州教育行政官資格. 一般社団法人京都府情報産業協会会長,一般社団法人全国地域情報産業団体連合会(ANIA)会長,一般社団法人日本IT団体連盟代表理事・筆頭副会長,一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)理事. 本会2021年度-2022年度理事(IT産業連携担当).
[抱負] 人類社会全体のデジタル化の加速を担える優れた人材を獲得し育成することは,より一層の急務です. 2020年,一般社団法人情報処理学会と一般社団法人日本IT団体連盟(IT連盟)は,協力事業に関する協定を締結しました. 本会とIT連盟とが緊密な連携・協力を図ることは,我が国における「真の産学協同」の実現に繋がるものと確信しております. 「学び」と「仕事」の往来により,多くの方々がさらにスキルアップすることのできる機会の拡充,「学習の成果」を産業界が適切に評価することができる方策の具体化等に,本会の一員として,またIT連盟の筆頭副会長(IT教育・人材育成委員会管掌者)として,微力ながら尽力させていただく所存でございます.

■理事[教育担当]
湊 真一(MINATO, Shin-ichi)(京大1988卒)
京都大学大学院情報学研究科 教授
[略歴] 1990年京都大学大学院修士課程修了 . 1995年同博士課程(社会人)修了. 1990年よりNTT研究所に勤務. 2004年北海道大学助教授. 2010年より同教授. 2018年より京都大学教授(現職). 2018年度-2019年度 本会論文誌担当理事 . 2020年度本会英文論文誌JIP編集長 . 2021-2022年度本会事業担当理事. 2018年より日本学術会議連携会員.
[抱負] 新型コロナウイルス発生以降, 様々な社会活動のオンライン化が急速に進み, 学会を取り巻く環境も大きく変化しました. 全国大会等のイベントも約2年間は完全オンライン開催となり, 今年度になってようやく一部対面でのハイブリッド開催が可能となってきました. 対面での学会活動の重要性とありがたみを痛感する昨今ですが, 一方で, オンライン化以降, 全国大会の講演数や参加者数が大幅に増加しており, これまで仕事や家庭の事情で参加が難しかった会員が新たに参加可能になった側面もあったと見られています. 情報処理学会は, 情報分野で日本を代表する学会として, 単なる学問の交流の場としてだけでなく, 情報技術を活用することで日本社会の新しい形を作っていく役割も担っていると思います. もしも当選させていただいた場合には, 学会理事としての活動を通じてこれからの時代を作っていくお手伝いができればと思っております.

■理事[技術応用担当]
吉濱佐知子*(YOSHIHAMA, Sachiko)(青学大1993卒)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 ビッグデータコンサルタント
[略歴] 2001年より米IBMのワトソン研究所,2003年より日本IBM東京基礎研究所で情報セキュリティ関連,新興国向け研究戦略策定,AIやブロックチェーン技術を活用した金融業界向けの研究開発等を担当.2022年6月より現職.本会理事(2021年度-2022年度), 本会シニア会員,ACMおよびIEEE会員.博士(情報学).
[抱負] 情報システムが社会の重要なインフラとなり,人々の生活や社会のありかたに大きな影響もたらす一方,日本ではDXやダイバーシティへの取り組みが遅れており,一層の推進の必要性が叫ばれています. 情報処理学会は研究者や学生だけでなく,より幅広い技術者層に情報発信を行い,また社会に対する提言を行うなど,様々な角度から情報技術の振興を行うための活動を行っていますが,今後本会の担う役割はますます大きなものとなっていくと考えます. 私は2021年から総務理事として情報処理学会の運営や企画を担当し,特に倫理綱領の改訂や普及,ダイバーシティ宣言の作成に貢献させていただきました. また業務では日系IT企業,海外および日本の外資系IT企業の研究所,そして現職のクラウド事業者でのITコンサルと,長年様々な立場で情報技術に関わってきました.これまでの経験を生かして,産業界と学術界の連携を促進するとともに, 多様な人材が活躍できる社会の実現にむけて,情報処理学会の発展に貢献したいと考えています.

■理事[論文誌担当]
稲見 昌彦(INAMI, Masahiko)(東工大1994卒)
東京大学先端科学技術研究センター 教授
[略歴] 1999年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了,博士(工学).電気通信大学,慶應義塾大学等を経て2016年より現職.人間拡張工学,エンタテインメント工学に興味を持つ.文部科学大臣表彰若手科学者賞などを受賞. JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究総括,IPA未踏PM,日本学術会議連携会員等を兼任. 本会会誌編集長(2018年度-現在),本会フェロー.
[抱負] Society5.0や人間拡張技術により,我々は自らの能力を自在に設計できるようになりつつあります.そこで重要となるのが,多くの人が魅力的と思うような目標と場をデザインし,広めることだと思います.私は,本学会エンタテインメントコンピューティング研究会の設立や,新世代企画委員として若手研究者の登竜門『IPSJ-ONE』の立ち上げに関わりました.また会誌編集長として異なる分野をつなぐ横糸としての情報学の役割を,特集等の企画を通して発信するとともにNoteやtwitterなどの活用,技術書典やバーチャルマーケットへの出展など,紙面以外での会員コミュニケーションや将来の会員候補者へのアプローチを行って参りました.将来を担う若手研究者や企業技術者たちにとって本学会が魅力的と思える場であり続けるには,新たなチャレンジを行い続けるとともに,限られたリソースを有効活用するために過去の取り組みを整理し新陳代謝を促すことが必要と考えます.皆が集まりたくなり,新たな仲間に出会える楽しい学会であり続けるためのお手伝いをできればと思っています.

■理事[長期戦略担当]
大場みち子*(OBA, Michiko)(日本女大1982卒)
京都橘大学工学部情報工学科 教授
※理事会からの推薦
[略歴] 1982年(株)日立製作所入社. 知識工学応用研究, ミドルウェア開発に従事. 2010年より現職.知的行動の記録と分析などの研究に従事. 2001年大阪大学大学院博士後期課程修了.博士(工学).日本学術会議会員. 本会フェロー, 理事(総務担当2009年度-2010年度, 事業担当2015年度-2016年度), デジタル・ドキュメント研究会主査などを歴任.
[抱負] 情報システムやネットワークは社会を支える重要なインフラとなり,AI・IoT・XRなどの情報技術が社会を劇的に変化させています.本会は情報処理に関する権威ある学会として,この画期的な社会変化の一翼を担ってきました. 本会では総務理事,企画理事,デジタル・ドキュメント研究会(現ドキュメントコミュニケーション研究会)主査他を歴任し,現在はドキュメントコミュニケーション研究会幹事,アクレディテーション委員,特集論文編集委員などを担当しています. 大学では研究の他、実践的IT人材育成教育にも力を注いできました. 日本学術会議では情報学やダイバーシティ推進での社会貢献を目指して活動しています.本会が継続的に発展し,社会に貢献するためには長期的展望に基づいて,本会の活動が社会に新しい価値を生み出しつづけ,広く社会に認知される仕組みづくりが必要です.企業での研究開発,マネジメントと大学での研究,IT人材育成,当会での活動など産学両面での経験を活かし,本会の継続的発展のための仕組みづくりと実行・推進に熱意を持って取り組みたいと考えています.
■理事[調査研究担当]
緒⽅ 広明(OGATA, Hiroaki) (徳島大 1992卒)
京都大学学術情報メディアセンター 教授
※調査研究運営委員会からの推薦
[略歴] 1995年徳島大学工学部知能情報工学科助手.1999年同講師.2001年同准教授を経て,2013年九州大学基幹教育院教授.2017年4月より現職.専門は教育工学,教育データ科学,ラーニングアナリティクス等.本会では教育学習支援情報システム主査などを歴任.
[抱負] COVID-19,GIGAスクール構想などで教育の情報化が加速しています.私は,教育データの収集・分析ための情報基盤システムLEAF/BookRollを開発し,国内外の初等中等教育並びに高等教育において教育データ科学,学習分析(ラーニング・アナリティクス)の研究に従事してきました.これまでの教育DX(デジタルトランスフォーメーション)の経験を生かして,学会全体のDXに貢献したいと思います.

■理事[総務担当]
鎌田真由美*(KAMATA, Mayumi)(横国大1986卒)
日本マイクロソフト(株)コンサルティングサービス事業本部エリアソリューションアーキテクチャ 本部長
[略歴] 日本アイ・ビー・エム株式会社にてSEおよびプロジェクトリーダーとしてSIビジネス担当後, 東京基礎研究所にてサービスリサーチ分野のマネージャー, 米国IBMワトソンリサーチにて技術戦略コアメンバーを務める. 2013年より日本マイクロソフト株式会社にてクラウド関連ビジネスに携わる. 専門分野はソフトウェア工学, 特に要求工学.
[抱負] 2020年から技術応用理事として特に実業界の方々向けにセミナーをご提供するなどの活動を担当させていただきました. コロナ禍の最中に理事として就任したこともあり,2年間に非常に多くのことを経験させていただきましたが,特に日本のDX推進の必要性がかつてなく強く叫ばれる今,研究と実務の間の架け橋となる役割が日本には必要であり,それが情報処理学会に期待されていることを痛感いたしました.情報技術は常に発展中であり,世界がしのぎを削る最先端基礎研究も,人々の生活を支える情報インフラも,エンターテインメントで生活を彩る応用技術もあり,夢と興味の尽きないエリアです.情報処理学会の仕事を通じてより多くの方に貢献できるよう,微力ではありますが引き続き力を尽くしたいと考えております.

■理事[調査研究担当]
岸 知⼆(KISHI, Tomoji) (京大 1980卒)
早稲田大学創造理工学部経営システム工学科 教授
※調査研究運営委員会からの推薦
[略歴] 京都大学修士課程,北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)博士後期課程修了.博士(情報科学).NEC,JAISTを経て2009年より現職.専門はソフトウェア工学.本会では,ソフトウェア工学研究会主査,論文誌編集委員を務める.1998年山下記念研究賞,2010年学会活動貢献賞,2017年標準化貢献賞.
[抱負] 情報技術は私たちの日常生活のおよそすべての分野において不可欠の存在となっていますが,それと同時に大変なスピードで進化を続け,また変化をしています.私の関わるソフトウェア分野では研究開発と実務への適用が常に同時進行しており,大きな価値や利便性をもたらす一方で,それが安全性,セキュリティ,プライバシー,さらには人間の知性そのものに対して及ぼす影響について,使いながら判断しなければならない状況を作り出しています.そうした中,学会には多様なステークホルダの立場を理解しつつ,情報技術に対する見識に基づいて公正かつ適切な情報を発信することが求められています.私は企業に20年間在籍し,その後大学に移籍し研究・教育活動に従事してきました.また専門分野の国際会議の運営や標準化活動にも長らく関わってきました.こうした経験を踏まえ,学会活動にいくらかでも貢献できればと考えております.
■理事[事業担当]
木村 朝子*(KIMURA, Asako)(阪大1996卒)
立命館大学情報理工学部 教授
[略歴] 1998年大阪大学院基礎工学研究科博士前期課程修了,2000年博士後期課程中退.同年,同大学助手,その後,立命館大学理工学部助教授,立命館大学情報理工学部メディア情報学科准教授等を経て,現在,同教授.博士(工学).実世界指向インタフェース,複合現実感,ハプティックインタフェースの研究に従事.
[抱負] この十数年の間に若手研究者のための公募のほとんどが任期付きとなりました.新しいポストを得るためには多くの業績が求められ,国内学会での発表よりも国際学会での発表が評価される.そんな中,国内学会の論文誌,研究会,シンポジウム,大会に求められる役割も変わってきているように感じます.私自身は,これまでヒューマンコンピュータインタラクション研究会で活動し,シンポジウム「インタラクション」の運営・改革などに取り組んで参りました.情報処理学会は,読みやすい学会誌やジュニア会員制度の導入など,他学会に先駆けた新たな取り組みに意欲的に挑戦している学会だと思います.理事のみなさんの抱負の中には,挑戦や発展という言葉が沢山登場します.私も,社会や会員のニーズを踏まえた運営,新しいアイディアや仕組みの導入などに積極的に取り組めればと思っています.微力ながら本学会の活動のお手伝いをさせていただければと思います.

■理事[会誌/出版担当]
⾼岡 詠⼦*(TAKAOKA, Eiko)(慶大 1990卒)
上智大学理工学部 教授
[略歴] 日本学術会議連携会員, 本会シニア会員. 2016年度-2018年度/2021年度-2023年度理事(教育), 2010-16年会誌編集委員,2012-16年コンピュータと教育研究運営委員会委員,2012-17年論文誌編集委員,2014-16年論文誌教育とコンピュータ編集委員会委員, 2012年-初等中等教育委員会委員(2019-幹事), 2015年-情報処理教育委員会, 2015年-情報処理に関する法的問題研究グループ運営委員会主査等を歴任.2007年度山下記念研究賞,2014年度学会活動貢献賞 受賞. 慶應義塾大学大学院計算機科学,博士(工学). 教育とコンピュータ, 医療看護介護用Web/スマフォアプリ等開発と運用に従事.
[抱負] 2016-18年度/2021-23年度の2回, 教育担当理事を務めました. この間, 文部科学省の2つの委託事業において担当責任者として本会の情報教育のプレゼンスを高めてきました. また2025年度からの大学入学共通テストに「情報I」を組み入れる動きに関して, 本会が的確なタイミングで意見表明を出すために尽力してきました. 本会は,文部科学大臣から教員免許状更新講習の開設者として指定を受け,2014年度より教員免許状更新講習を実施してきました.2022年7月1日に教員免許更新制が廃止されましたが,本会が, 文部科学省等と連携しながら今までの教員免許状更新講習の内容を発展させた教員研修の実施に取り組むことに, 情報科教育・研修委員会委員長として現在も尽力しております. 今後, 情報教育は社会のあらゆる場所において重要な役割を担うことは明らかで, 本会の情報教育における成果を社会に浸透させていくための時期であろうと思います. 本会の活動を通して社会に貢献したいと存じます.

■理事[財務担当]
千葉 直⼦(CHIBA, Naoko)(東工大1998卒)
日本電信電話(株)社会情報研究所 主席研究員
[略歴] 2000年東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了,同年NTT入社.入社以来研究所にて電子認証システム,セキュリティ社会科学,サイバーセキュリティの研究開発に従事するとともに,事業会社にてシステムセキュリティ監査制度の立上げに従事.
[抱負] 情報処理技術への依存度が高まる社会のなかで,老若男女あらゆる人々が,技術の生み出す価値の恩恵を受けられるように,技術の社会受容性を高めることを私は研究開発活動のなかで長年重視してまいりました.情報処理に関する学術および技術の振興をはかる本会の活動を通して, 情報処理技術に関わる人や社会がよりポジティブな方向へ向かうよう,尽力していきたいと思っております.

■理事[企画担当]
塚本 昌彦(TSUKAMOTO,Masahiko)(京大1987卒)
神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 教授
[略歴] 1989年京大・工・修士修了,同年シャープ入社, 1995年阪大・工・講師, 翌年助教授, 2004年神戸大・工・教授, 現在に至る. 工博, ウェアラブル関連NPO(2つ)の理事長・会長. ウェアラブル・ユビキタスシステムと応用を研究. 2001年よりHMD装着生活. 本会会誌元編集長(2014-17年度), 元理事(2009年度-2010年度) , 元デジタルコンテンツクリエーション研究会主査(2012-15年).
[抱負] 「1年後に街中を歩く人が皆HMD(スマートグラス)を装着している」20年以上前から言い続けていますが, これまでずっと外してきました.「2030年に私はサイボーグになる」ここ10年ぐらい言い続けていますが, これはもしかしたら当たるかもしれませんので, なんとか頑張りたいと思います. 「2045年に科学技術と社会さらには人類自体も大変革を起こす」よく言われている「シンギュラリティ論」の一つで, 私はこれを支持しています. 最近AIが急成長し, 多くの人の予想より早くAIが人間を追い越すレベルにまで到達しそうな勢いです. もしそうなれば, その後はあっという間に遥か高いレベルの知能に到達することが考えられます. もしかしたら「シンギュラリティ」は2045年よりずっと早いタイミングで来るのかもしれません. このような人類の大変革の始まりかもしれないタイミングに, 学会としてできること, やらないといけないことはたくさんありそうです. ワクワクする未来を創っていくことに少しでも貢献したいと望んでいます.
■理事[長期戦略担当]
寺⽥ 努(TERADA,Tsutomu)(阪大1997卒)
神戸大学大学院工学研究科 教授
※理事会からの推薦
[略歴] 1999年阪大・工・修士修了.博士(工学).現在,神戸大学大学院工学研究科教授.NPO法人ウェアラブルコンピュータ研究開発機構理事,NEC研,三菱先端研,ATR,JSTさきがけ等の研究員を兼任.ウェアラブル・ユビキタスコンピューティングの研究を推進.2016年度-2017年度・2018年度-2019年度本会理事, 本会山下記念研究賞,長尾真記念特別賞,2022年論文賞等110件の受賞.
[抱負] 機械学習技術やウェアラブル技術の発展は,コンピュータ分野に閉じた話でなく,我々の生活に極めて強力な影響を与えています.このような状況では情報処理に関する研究も効率や性能を追求するのではなく,情報技術と人間の心身の関係を含めて社会に与える影響を考慮する必要があり,そのためにはさまざまな分野との連携をはかりながら長期的なビジョンをもって情報技術の未来を示していかなければなりません.情報技術の浸透は正負両面の効果を生むため,情報技術は「いいもん」であることを積極的に発信する取り組みも必要であると考えます.本会が社会における「情報処理」の受容性を高め,人々への情報処理技術の普及啓蒙を加速すべく,理事として推薦頂きました.これまで私は本会で10研究会において主査・幹事・運営委員を務め,学会発展に向けて長期的かつ迅速に活動できます.また,私はNPO法人理事や地域での情報提示システムの実運用に携わるなど,情報技術を社会に浸透させるための取組みを多数行ってきました.これまでの活動の経験を活かし,情報処理学会の発展に貢献したいと考えています.

■理事[教育担当]
遠⼭紗⽮⾹*(TOHYAMA, Sayaka)(中京大2005卒)
静岡大学情報学部 講師
[略歴] 博士(認知科学).2009年静岡大学技術職員,2014年同教育学部特任助教,2018年同情報学部助教,2021年より現職.専門は情報教育,学習支援,学習評価.本会初等中等教育委員会副委員長,論文誌「教育とコンピュータ」編集委員,情報教育シンポジウム(SSS2023)プログラム委員長.
[抱負] 私は初等中等教育での情報教育を推進してきました.シンポジウムでは,より良い情報教育を実現するためのビジョンや先行事例の提供を,ジュニア会員の方には,中高生情報学研究コンテスト等を通じて互いの能力を一層高めるための交流促進を,それぞれ行ってきました.また,文部科学省「情報Ⅰ」学習会や教育委員会主催の研修会等での講師経験を通じて,教育行政担当者や情報教育の実践者と交流を深めてきました.今後は,初等中等教育から高等教育まで一貫した情報教育を当たり前のものとして社会に定着させる活動が求められるものと思われます.そのためには本会が有する専門的知見を活かして,探究的な情報教育を一層推進すること,ジュニア会員のさらなる獲得と発表・交流の推進を継続することが重要だと思います.また,情報入試は,情報教育の観点で高大接続のより良い在り方を考えるうえで欠かせないテーマだとも思います.私自身の学習・教育に関する専門性も発揮しながら,本会が果たす役割がさらに大きなものになるよう,貢献できればと思います.

■理事[技術応用担当]
⼭下 直美*(YAMASHITA, Naomi)(京大1999卒)
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 特別研究員
[略歴] 2001年京都大学大学院情報学研究科修士課程修了,同年NTT入社.2006年京都大学大学院情報学研究科博士課程修了.博士(情報学). ウェルビーイングの向上,インクルーシブな社会の実現に向けた情報技術の研究開発に従事.長尾真記念特別賞受賞(2011)などを受賞.ACM SIGCHI Vice President (2021-), 日本学術会議連携会員, CHI 2025 大会長等を兼任.
[抱負] 経済格差の拡大や思想の分断により社会が不安定化する中, 情報技術を用いて多様な社会問題を解決し, サステイナブルな社会を構築することが期待されています. 本会においても, 異なる分野の研究者が集い, 自由に意見交換をおこなえる場にすることで, こうした課題への対応に貢献することが重要だと思います. 私はこれまで, 人間中心的なアプローチによって, 異文化間交流や精神疾患を抱える人々の社会参加を支援するコミュニケーション技術の研究に取り組んできました. 海外の学会においても, インクルーシブなコミュニティ形成のための活動に携わっています. 本会が, 産業界, 学術界, 国籍, ジェンダーなどの枠を超え, 多様性を活かし, 活気ある未来社会への貢献を目指す場となるよう, 私の経験が少しでもお役に立てばと思っております.

■監事
中野美由紀*(NAKANO, Miyuki)(東大1981卒)
情報・システム研究機構/津田塾大学 理事/教授
[略歴] データ工学に興味を持ち, 高性能データベース, 大容量・高速ストレージ, 省電力データベース, ビッグデータ支援プラットフォーム等の研究に従事.1985年に東京大学生産技術研究所, その後, 芝浦工業大学, 産業技術大学院大学を経て津田塾大学に在籍.情報処理学会 事業担当理事(2018-2019年度) , 技術応用理事(2011-2012年度), セミナー推進委員会委員長(2012年)等歴任.
[抱負] 「新型コロナ」は収束を見せず, 戦争や温暖化など地球規模の課題は留まることをしりません。そのなかで, 情報処理技術はまさに人々の生活, 社会を維持するために欠かせないものとして利用されています.世界中のデータが様々な観点から利用される現在, 多くの社会集団にとって情報処理を適切かつ適応的に利用し, ツール,プラットフォームとして構築・維持することが期待されています.我が国でもデジタル庁が創設され,情報処理技術はあらゆる分野から大きな期待が寄せられています.本学会は, 先端の情報処理技術を学術的かつ社会的な観点から日本社会に発信,牽引すべき立場にあり,急激な変化が世界的に生じる現在において,監事は, コンプライアンスを重視しつつ学会を監査する責にあると 同時に, 本学会から社会に向けて情報技術の発信を支援することができると考えます.昨年度来から積み重ねてまいりました監事の経験に, 今までに務めました本学会の各種委員, 委員長,理事等の経験および,日本データベース学会, 電子情報通信学会等の経験を生かし, 「新型コロナ」以降に向けた新たな学会における健全かつ適正な学会活動のあり方を支援・貢献したいと考えております.

■監事
長谷川輝之(HASEGAWA, Teruyuki)(京大1991卒)
KDDI(株)オペレーション技術開発部 グループリーダー
[略歴] 1993年国際電信電話入社,以来研究所で高速通信プロトコルの研究,2017年よりKDDIで運用システム開発に従事.博士(情報理工学).本会事業担当理事,論文誌運営委員会NWG主査,モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム研究会幹事,デジタルコンテンツクリエーション研究会運営委員,会誌編集委員,DICOMO実行委員等を歴任.本会フェロー.電波功績賞受賞.
[抱負] スマホとインターネットは現代の日常生活になくてはならない重要なインフラとなっています. 大規模なインフラを安定的・持続的に提供する,また, DX・ビッグデータ・AIなどの活用に基づく「情報と実世界との融合」でより豊かな社会の実現に貢献するなど, 情報処理技術者が活躍する場は益々広がっています. 一方で, 個々の技術が複雑化・ブラックボックス化しており, 将来を担う学生や若手技術者がその仕組みを深く理解し自ら発展させていく機会はむしろ少なくなっているようにも感じています.学会は,情報処理技術を身近にかつ深く理解する場を継続的に提供する責任があり,このためには,持続可能な財務基盤や稼働提供の仕組みを弛むことなく整えていく必要があります.本会事業担当理事・各種国際会議の運営・企業でのシステム開発などの経験を活かし,コンプライアンスや財務規律を遵守しつつ,学会全体の取り組みを俯瞰し,攻めと守りのバランスの取れた学会運営を支えるべく尽力して参ります.
※上記は立候補当時の内容です