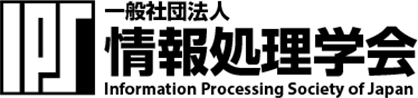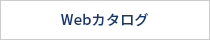「DRAMの設計余裕を活用した低レイテンシ化・低消費電力化手法とその制御法の研究動向」
2023年度論文賞受賞者の紹介
DRAMの設計余裕を活用した低レイテンシ化・低消費電力化手法とその制御法の研究動向
[情報処理学会論文誌 コンピューティングシステム Vol.16 No.1, pp.14-28]
[論文概要]
コンピュータのメインメモリを構成する DRAM のランダムアクセスレイテンシと消費電力は大きな課題である.これに対し,DRAM の設計余裕を活用した低レイテンシ化,低消費電力化が着目されている.DRAM 内の電気的操作は最悪ケースを想定し余裕を持ったタイミングで行うよう設計されている.そのため,たとえば規定の待機時間を待たず操作しても多くの場合正常に動作し,これを利用するとレイテンシと消費電力が削減できる.これを本論文では「DRAM の設計余裕活用技術」と呼び,その動作原理,適切な制御法の研究動向,残された技術的課題を詳細に論じる.
[受賞理由]
本論文は,DRAMの動作原理から最新の設計余裕活用の研究成果までを丁寧にまとめていることから,アーキテクチャ分野の研究者にとって大変有用な一報となっており,このようなサーベイ論文は大変貴重である。DRAMの低レイテンシ化と低消費電力化について,特にレイテンシ・電力・誤差の面のトレードオフについて,独自のアーキテクチャ的側面からの視点を活用しつつハードウェアとソフトウェアの両面から質の高い調査がなされており,またその結果や挑戦すべき課題について非常にわかりやすくまとめられている。微細化されたプロセスにおいて,設計マージンを活用する技術は非常に重要であり,これから重要性が増すと考えられる分野に関する本サーベイは,他の研究者を呼び寄せ当該研究分野を活性化することにも貢献することが期待される。以上のことから,本論文は論文賞受賞にふさわしいと判断し,ここに推薦する。

穐山 空道 君
2010年京都大学工学部情報学科卒.2015年東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻修了.博士(情報理工学).日本電信電話株式会社,産業技術総合研究所,東京大学を経て,2022年4月より立命館大学 情報理工学部 セキュリティ・ネットワークコース 准教授.メモリシステム,性能分析,仮想化技術等の研究に従事.

山田 淳二 君
2010年信州大学工学部情報工学科卒.2017年東京大学大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻修了.博士(情報理工学).2004年より2015年まで,エルピーダメモリ株式会社(現マイクロンメモリジャパン株式会社)にてDRAMの開発に従事.2017年より,東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)にてNANDフラッシュメモリの開発に従事.

塩谷 亮太 君
1981年生.2011年 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 博士課程修了.博士(情報理工学).2011年 名古屋大学大学院 工学研究科 助教.2016年 同大学院同研究科 准教授.2018年 東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 准教授,現在に至る.コピュータ・アーキテクチャや基盤ソフトウェアなどの研究に従事.